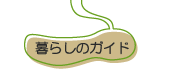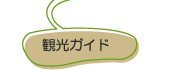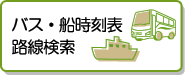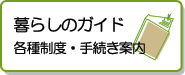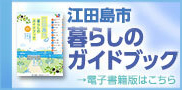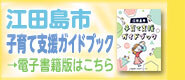児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。
令和6年10月からの拡充内容については、こちらをご覧ください。
制度の概要
支給対象
江田島市に住所を有し、0歳~高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母のうち、原則として、所得が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方が受給者となります。
支給要件
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために日本国内に住所を有しない児童で、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給月額
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子 |
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校生 | 10,000円 | 30,000円 |
※親等の経済的負担がある22歳(大学生年代)までの子のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
手当の支給時期
原則として年6回(偶数月)、受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。
| 支給月 | 支給対象の月 | 支給日 |
| 4月 | 2月・3月分 | 10日 ※10日が休日の場合は直前の平日 |
| 6月 | 4月・5月分 | |
| 8月 | 6月・7月分 | |
| 10月 | 8月・9月分 | |
| 12月 | 10月・11月分 | |
| 2月 | 12月・1月分 | |
認定請求の方法
お子様が生まれたり、他市町村から江田島市に転入したときは、速やかに認定請求(申請)をしてください。(公務員の場合は、勤務先に申請)
児童手当は、原則として申請をした月の翌月分から支給します。出生日や転入日(前住所地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日または転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、御注意ください。
【受付窓口】
子育て支援課(にこ♡にこハウス)、江田島市役所本庁(2階 社会福祉課)、各市民センター(大柿市民センターを除く。)又は三高支所
【必要なもの】
・請求者の健康保険の資格情報が分かるもの(資格情報の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険証の写し(令和7年12月1日ま
で)、マイナポータルの保険情報確認画面のスクリーンショット、年金加入証明書)
・請求者名義の預金通帳(普通預金口座に限る)
・請求者と児童の住所が異なる場合は、別居している児童の個人番号が確認できるもの
・外国籍の方は、在留カードなどの写し
・申請者及び配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・本人確認できるもの(免許証など)
※その他、場合によって必要な書類があります
次の場合は手続きが必要です
手続において本人確認資料等が必要です。(例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
| 必要な手続詳細 | 届出 | 必要なもの | 備考 |
|
・転入、出生などにより、新たに受給資格が生じたとき ・公務員でなくなったとき |
認定請求書 |
・上記「認定請求に必要なもの」参照 ・所属庁での児童手当の消滅日が分かるもの(辞令等) |
|
|
・受給者が他の市町村に転出したとき ・受給者が収監されたとき |
受給事由消滅届 | 転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村において認定請求手続きが必要です。 受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者と児童が引き続き国内に居住する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に、配偶者からの認定請求手続きが必要です。 |
|
|
・受給者の単身赴任、児童の進学等で受給者と児童が別住所になったとき |
別居監護申立書 | 対象児童の個人番号が分かるもの | |
| 第2子以降の出生などにより、支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書(増額) | 額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください(15日特例あり)。 | |
| 3人以上の子を養育している受給者のうち、大学生相当の兄姉を養育するとき |
・額改定認定請求書(増額) ・監護相当・生計費の負担についての確認書 |
額改定認定請求をした月の翌月分から手当額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください(15日特例あり)。 | |
|
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき ・3人以上の子を養育している受給者のうち、大学生相当の兄姉を養育しなくなったとき |
額改定届(減額) | ||
| 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 | ||
| 児童が施設に入所したときや、里親に委託されたとき | 額改定届(減額)または受給事由消滅届 | 児童手当は施設設置者や里親などに支給します。 | |
| 児童が施設を退所したときや、里親の委託が解除されたとき | 認定請求書または 額改定認定請求書(増額) |
上記「認定請求に必要なもの」参照 | 退所などした日の翌日から15日以内に認定請求手続きをしてください。 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | 辞令書の写し | 公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先に認定請求手続きをしてください。 |
|
・受給者や児童の氏名・住所・電話番号が変更したとき ・受給者の加入する年金が変わったとき |
氏名・住所等変更届 | 婚姻や離婚等により、受給者が変更する場合は、現受給者の受給事由消滅手続き及び新受給者の認定請求手続きが必要になります。 | |
| 振込口座を変更するとき | 金融機関変更届 | 預金通帳 | 手当支払月の前月末までに手続きをしてください。 |
| 受給者が死亡した場合 | 未支払請求書 | 児童名義の預金通帳 | 受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内に児童の養育者からの認定請求手続きが必要です。 |
現況届の提出について
現況届は、原則不要です。
ただし、次に該当する方は、引き続き、現況届が必要です。
提出がない場合は、6月以降の手当の支給が停止されますので、御注意ください。
① 配偶者からの暴力等により、住民票が江田島市以外にある方
② 支給対象児童の戸籍がない方
③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
④ 支給対象児童の住民票が江田島市にない方
⑤ 高校3年生に相当する年齢以下の児童で、江田島市に住民票がない者を養育している方
⑥ 第3子以降の多子加算の対象となる、大学生相当の子を養育している方(※4年生大学生の場合は提出不要)
⑦ その他、提出の案内があった方
※毎年7月頃に発送していた児童手当認定(継続)通知書については、令和7年度から廃止します。
現況審査の結果、支給金額が変更する場合や、受給資格が消滅する場合は通知書によりお知らせします。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄附を行う手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
江田島市福祉保健部子育て支援課 〒737-2122 江田島町中央四丁目18番28号
TEL.0823(42)2852
FAX.0823(42)3322
関連ファイル ダウンロード
認定請求書 (494 KB)
受給事由消滅届 (81 KB)
別居監護申立書 (47 KB)
額改定認定請求書/額改定届 (135 KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (91 KB)
氏名・住所等変更届 (260 KB)
金融機関変更届 (58 KB)
未支払 児童手当 請求書 (114 KB)
Adobe Readerのダウンロードへ