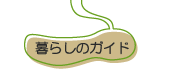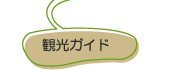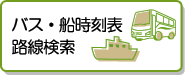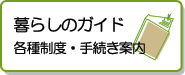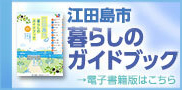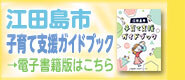介護保険制度~みんなが支える制度です~
介護保険は、介護が必要になったときでも安心して暮らせるように、介護を必要とする人やその家族の負担を、社会全体で支え合うためにつくられた制度です。
40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスを利用することができます。
40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割~3割)を支払って、介護サービスを利用することができます。
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
介護保険の対象となる特定疾病により、介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できます。
介護サービスとは
介護サービスには、大きく分けて①「居宅サービス」②「地域密着型サービス」③「施設サービス」の3つがあります。介護認定の結果によっては利用できないサービスもあるため、ご注意ください。
| 居宅サービス | サービス内容 |
|---|---|
| 訪問介護 |
利用者の自宅に訪問し買い物や掃除、食事や排せつの介助などを行う。 |
| 訪問入浴介護 | 利用者の自宅に訪問し、移動式浴槽を用いて入浴などを行う。 |
| 訪問看護 | 利用者の自宅に訪問し、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置などを行う。 |
| 訪問リハビリテーション | 医師の指示により、利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・支援などを行う。 |
| 居宅療養管理指導 | 利用者の自宅に訪問し、療養上の管理・指導・助言などを行う。 |
| 通所介護 | 施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで行う。 |
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療施設などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上のために日帰りでリハビリテーションを行う。 |
| 短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを行う。 |
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設や医療施設に短期間入所して、医学的な管理の下で医療上のケアを含む日常生活上の支援などを行う。 |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームなどにおいて、入居者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を提供する。 |
| 福祉用具貸与 | 利用者に、車椅子や特殊寝台などの福祉用具をレンタルする。 |
| 特定福祉用具販売 | 利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する。 |
|
住宅改修費支給 |
利用者の自宅に、手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修を行う。 |
|
地域密着型サービス
|
サービスの内容
|
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 1つの拠点で訪問・通所・短期入所の全サービスを提供する。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(※) | 「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を組み合わせて提供する。 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
|
日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と緊急時の随時訪問による介護と看護を一体的に行う。 |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで行う。 |
| 認知症対応型通所介護 | 施設に通ってきた認知症の方に、入浴・排せつ・食事等の介護、健康状態の確認、機能訓練などを行う。 |
| 夜間対応型訪問介護(※) | 夜間の定期的な訪問や緊急時の随時訪問による介護を行う。 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の方が共同で生活する住居(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。 |
|
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
定員が29人以下の特別養護老人ホームの入所者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(※) | 定員が29人以下の介護付有料老人ホームなどにおいて、入居者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を提供する。 |
| 施設サービス | サービス内容 |
|---|---|
|
介護老人福祉施設 |
在宅生活が困難な人が入所し、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う。 |
| 介護老人保健施設 | 在宅復帰できるように一定期間受け入れ、医療処置とリハビリテーションを中心とした介護等を提供する。 |
| 介護医療院(※) | 長期にわたり、療養が必要な方を受け入れ、医療的ケアと介護を一体的に行う。 |
※現在、江田島市内に介護サービス事業所(施設)はありません。
介護サービス利用までの流れ
1 相談
高齢介護課や地域包括支援センターの窓口で相談します。
※高齢者の方が日常生活で困りごとを感じたときは、こちらもご活用ください。
生活支援情報冊子【えたじまのくらし楽々ブック~わがまち辞典~暮らしの便利帳】
2 申請
本人やご家族が、郵送や市の窓口で「要介護認定の申請」をします。地域包括支援センターの職員などに代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
① 介護保険被保険者証(【ピンク色】65歳以上の人のみ)
② 健康保険被保険者証または健康保険資格確認書
③ かかりつけ医の名前や医療機関の名称がわかるもの
3 認定調査と主治医意見書の依頼
介護認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について調査を行います。
また、市から主治医宛てに心身の状況について意見書の作成を依頼します。
認定調査の結果によるコンピュータ判定と主治医意見書を基に「介護認定審査会」で審査し、判定されます。
4 認定結果
① 自立(非該当)
② 要支援1・2
③ 要介護1~5
のいずれかの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
のいずれかの区分に分けて認定され、その結果を通知します。
5 ケアプランの作成
介護サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。
|
要支援1・2の人
|
地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に相談します。
|
|---|---|
|
要介護1~5の人
|
在宅生活をしながら、介護サービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所に相談します。
|
| 介護施設に入所して、 介護サービスを利用したい場合は、施設に直接入所の申込みをしてください。 |
6 介護サービスの利用
ケアプランに基づき、介護サービスを利用します。利用したサービス費用の1割~3割を支払います。
(所得により負担割合が異なります。)
介護保険料について
こちらを参照してください。